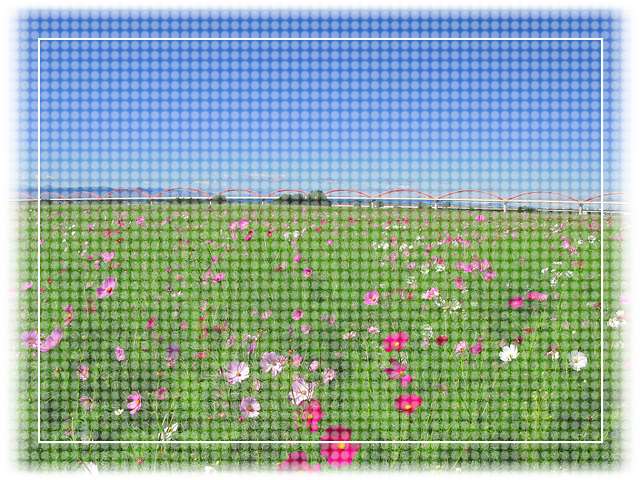「いつだって君を見ていたいんだ」
パーセプターがぼそりと呟き、ゴツンと音をたてて肩に寄り掛かってきた。
甘えでもない、睦言とも違う。真摯な響きに押し黙り、自分は、その告白じみた言葉に何と返すべきなのだろう?そもそもパーセプターは、なんの意図をもって自分にそんな事を言ったのだろう。と考えてみるが、ドリフトには一向にわからなかった。
ただ恋人の重みと、あたたかな温度を肩に感じながら、自分は、想われているのだ。という事を沁々と思った。
「君を箱にしまっておけたら良いのに。と」
「標本みたいにか?」
茶化したつもりだったが、パーセプターが大真面目に頷き返して来たので、また押し黙ってしまう。
恐れからではない、それがとても良い考えに思えてしまって、自分でも驚いてしまったからだ。
「真綿にくるんで、硝子の蓋をかけて他の誰にも見えないように、鍵をかけてしまっておきたいよ」
「あんたがそうしたいのなら、俺はかまわない。だが…」
俺の好きな時にあんたに会えないのは困りものだな。
そう答えると、パーセプターは少し残念そうに横目で見やり、肩を竦めて寄りかかっていた体を起こす。
「パーセプター」
「なんだい?」
「俺はけっこう本気だぞ」
「私は冗談だったがね」
ただの戯れだよ。
その割に淋しそうな横顔をするものだから、俺はもう一度、好きなようにして
構わないからな。と言って、パーセプターを強く抱き締めた。
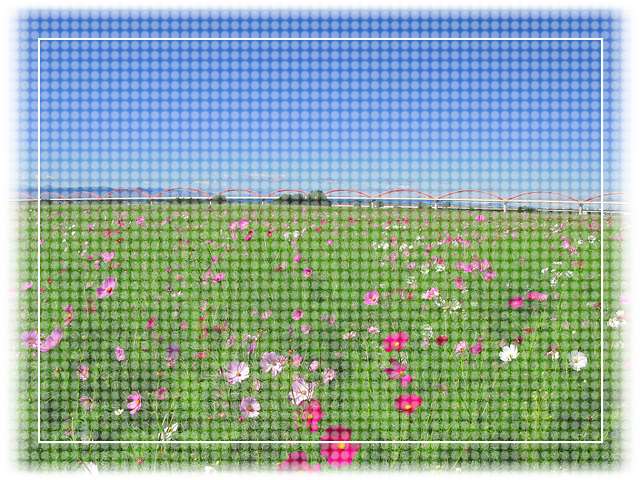
風にそよぐ秋桜の花。白、ピンク、濃紅(こいくれない)に赤紫、種々様々な彩りを見せるそれらを視界に収めながら、ドリフトは河川敷に寝転び、秋のぽかぽかとした日差しを浴びる。
冬の低く垂れ込めた雪雲や春の紗を広げたような霞空、真夏の焦がすような日差しと、白く迫る入道雲。それらと異なる秋の空は涼やかに蒼く、天高く馬肥ゆる…とは地球人の言葉だが、確かにひときわ広く感じる。
「ドリフト、ここに居たのか」
少し遠くから声を掛けられ、首をもたげて土手の上を見やれば、朝から論文をまとめる為に、黙々と机にかじりついていた筈のパーセプターが立っていた。
「パーセプター?今日は忙しいと聞いていたが」
「煮詰まってしまってね。息抜きさ」
パーセプターも集中力が切れる時があるんだな。と思わず口にすると、そりゃあ私だってそんな時もあるさ。と僅かに微笑みながら土手を下り、俺の横に腰掛けた。
「ご一緒してもよろしいかい?」
「あんたなら大歓迎だ」
それから幾ばくか他愛のない話をした。(パーセプターの研究の話となれば兎も角)お互い口数の多い方ではないからすぐに沈黙が訪れるが、その沈黙でさえドリフトは快いと思う。今二人の間に流れているのは、思いを確かめ合う前の、どこかソワソワとした、心許なく落ち着かない空気ではなく、穏やかで長閑な空気だから。
ふと寝転んでいたドリフトが背を起こし、傍らに咲く秋桜を一輪摘み取った。
「部屋の一輪挿しにでも活けるのかい」
「それもいいがやってみたい事がある」
やってみたい事?と首を傾げるパーセプターに、この間地球人がやっているのを見たんだ。と告げ、白い花びらを一つ、プチンと千切る。
「パーセプターは俺の事が…」
嫌い
好き
やってみたい事。の内容に合点がいったパーセプターは(珍しく)目を丸くして驚き、ついでくすくすと肩を揺らして笑い出した。
「…それは幼い子供か、年頃の少女がする事じゃないかい」
「そうなのか?…と、好き。で終わりだな」
あらかじめ枚数を数えてから始めたのだから、当然の結果だ。勿論パーセプターもその事に気付いている。だから占いなんて否論理的だ。なんて野暮な事も言わず、ただ笑ってくれている。
「お前さんは何時も私を驚かせるな」
「そうか?」
「だがどうせなら、こういうやり方の方が正確だと私は思うよ」
そう言って、パーセプターの指先が、赤紫色の秋桜を一輪手折る。
「ドリフトは私の事が…」
さてどうするのかと見ていると、パーセプターは思いもよらぬ事を始めた
好き
好き
好き…
好き。と紡がれる度に花びらがひとひらづつ散ってゆく。
そうしてパーセプターは最後のひとひらを摘み
「好き…。で終わりだね」
と言って俺に微笑んだ。
「…それはもう占いじゃないだろ」
「おや、もしかして外してしまったかな」
「いや、大当たりだ」
ああもう、きっと俺は永遠にパーセプターに勝てないんだろう。そんな気がする。
「パーセプター。あんたが好きだ。他の何よりも」
「私もお前さんが好きだよ。勿論一番にだ」
はやく私を奪ってよ
そのぎらぎらと光るオプティックと、彼の刃の切っ先はよく似ていた。
私に覆い被さったまま絶命した一回り大きな機体は、その力を失い、ずしりと重みを増す。刺し貫かれた胸部と、はね飛ばされた首の断面から溢れ出るオイルが、私の身体ををしとどに濡らした。
声は出なかった。呼吸も、指先も、思考回路さえも、凍りついたように動かなかった。
ず、と胸部から刀が引き抜かれ、物言わぬガラクタへと成り果てたそれが、乱暴に蹴り飛ばされるに至ってようやく、私の思考は動き出した。
「……ぁ」
途端に小さく震え出す指先、それを押し止めたくて、両の手を、ぎりと軋む程強く握り締めるが、震えは収まるどころか指先から腕、肩、全身へと広がってゆく。
「パーセプター」
優しい、声
覚束なく彷徨っていた視線が自ずと定まり、徐々にピントが合うにつれて、彼の姿も実を現していった。
「間に合って良かった」
ビュンと刀を一振りしてオイルを払い、両鞘に刀を収めた彼が跪き、ゆっくりと手のひらを差し出す。
「…怖かったのか」
いや、怖かっただろう。
そう言って彼は双眸を曇らせ、かたかたと震える私の手をとり、柔らかく包み込む。緊張で冷えた指先に、かれの暖かさがじんわりと染み渡る。
「ドリフト…ッ!」
その眼差しは穏やかで、アクアマリンに似た明るい色の瞳には、もう、あの、見る者を射竦め、恐れさせる殺意は無い。
「もう大丈夫だ」
惣花
「という訳で今宵は十三夜、栗名月にござるよ〜」
じゃーん、という彼のセルフ効果音と共に掛布が取り払われ、現れたのはこの1ヶ月程で随分見慣れた感のあるススキ、月見団子、そして今回は、艶々とした栗がこんもりと盛られている。
「なにがという訳かは知らないが、そうなのか、ついこの間は十五夜だの豆名月だの中秋の名月だの芋名月だの言っていたじゃかないか、君がお気に入りのジャパンに住む人々は、よほど月が好きとみえる」
丸々とした栗を1つ摘み、矯めつ眇めつ眺めながら呟くと、何が面白いのか、此方を向いたドリフトがくすくすと笑う。問い掛けのつもりで首を傾げて見せると。曖昧に笑って何でもないとはぐらかされた。
「さあ、夕げにしよう」
「おや、もう食べてしまうのかい?」
「いいや、拙者達の分は此方にござる」
彼が後ろ手に取り出した箱には(弁当箱と言うらしい)、栗ご飯と、茸と鶏肉の煮付け、そして胡瓜の漬け物が入っていた。
「外で…とは言っても甲板でござるが、ゆっくり月を見ながら食べましょうぞ」
「そうかい、なら私も何か持とう」
ならばと酒で満たされた徳利と、御猪口を渡され、並んで歩く事数分。船の甲板に出ると、澄んだ夜空に星が瞬き、時折雲が冷えた風に流されて頭上を通り過ぎていく。そして満月には少し早い、十三夜の月が白く静謐に輝いて、地上を照らしていた。
「月が綺麗でござるな」
「ああ、キレイだ」
月を見上げ、その光で淡く燐光を纏いながら、僅かに目を細めて微笑む君の横顔が、とてもキレイだと
下心ですがかまいませんか?